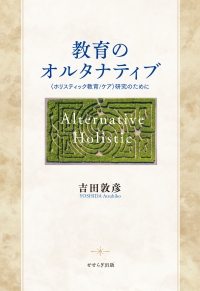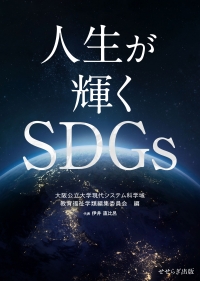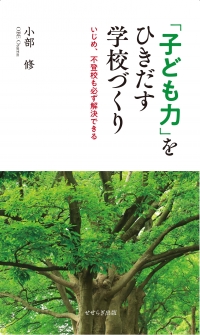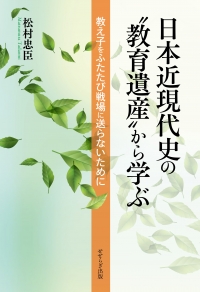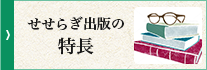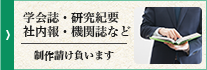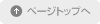−教育・子育て−
本書は、学位論文として2017年に執筆した内容に、その後の研究内容を加味・整理して出版するものである。
本書は、近年、教育と社会から疎外される子どもたちの深刻な荒みや自尊感情の喪失状況に着目し、その多様な要因の中から、とりわけ現在の学校教育・制度に内在している「一定」に基づく画一的な教育によって、事実上その「教育」から疎外や排除を受けている児童生徒がいること―そして、その子どもたちは、結果的に憲法二十六条の保障を享受しているとは言い難い状態で放置されている事態を、人権問題として提起するものである。
この問題解決に臨む基本的立場として、当該状況を、改めて子どもの立場から捉え直す視座の転換を行い、大人の都合で権利を肩代わりすることなしに、子ども自身によって、能力に応じた「教育を受ける権利」の保障として教育制度整備要求を行えることを提起する。具体的に、能力に応じた「学習要求」を可能にする制度創設の提起を行うことが目的である。同時に、制度創設を可能にする憲法上の理論的検討を学習権の今日的意義を明らかにしながら、また、子どもの権利条約の国際解釈を用いながら検討する。(「本書の概要」より)
本書は、近年、教育と社会から疎外される子どもたちの深刻な荒みや自尊感情の喪失状況に着目し、その多様な要因の中から、とりわけ現在の学校教育・制度に内在している「一定」に基づく画一的な教育によって、事実上その「教育」から疎外や排除を受けている児童生徒がいること―そして、その子どもたちは、結果的に憲法二十六条の保障を享受しているとは言い難い状態で放置されている事態を、人権問題として提起するものである。
この問題解決に臨む基本的立場として、当該状況を、改めて子どもの立場から捉え直す視座の転換を行い、大人の都合で権利を肩代わりすることなしに、子ども自身によって、能力に応じた「教育を受ける権利」の保障として教育制度整備要求を行えることを提起する。具体的に、能力に応じた「学習要求」を可能にする制度創設の提起を行うことが目的である。同時に、制度創設を可能にする憲法上の理論的検討を学習権の今日的意義を明らかにしながら、また、子どもの権利条約の国際解釈を用いながら検討する。(「本書の概要」より)
本書は、離婚後の子の福祉の観点から、離婚後の面会交流で元夫婦がどのような場合に面会交流が認められるか否か、また別居中・離婚後の監護に関する事項でどのような問題が生じうるかを論考および事例研究で検討したうえで、面会交流と離婚後の共同親権の要綱案を考察するものである。本書により、「忸怩たる思い」を抱くことなく、「晴れ間」が見えるようになれば、望外の喜びである。2024年4月 (「まえがき」より)
2023年11月発売
ダウン症児のおかあさんが、競争に疲れた保護者や先生方にお送りする1冊。
本書は2022年4月にアイエス・エヌから発売された『子どもたちはみんな多様ななかで学びあう』をせせらぎ出版から再発行したもので、内容は同じです。(一部装丁、本文中のデータに変更あり)
ダウン症児のおかあさんが、競争に疲れた保護者や先生方にお送りする1冊。
本書は2022年4月にアイエス・エヌから発売された『子どもたちはみんな多様ななかで学びあう』をせせらぎ出版から再発行したもので、内容は同じです。(一部装丁、本文中のデータに変更あり)
2023年11月発売
大好評の『走れ!児童相談所』シリーズ第2弾
里崎が勤務2年目を迎える中央子ども家庭センターに、あの田丸が異動になってやってきた。キャラの異なる二人はチームを組んでケースに対応する。困窮した家庭を支援する一方、力及ばず壁にぶつかることも経験。そんな二人が次に直面したのは、卑劣な性的虐待だった。
本書は2018年3月にアイエス・エヌから発売された『光に向かって ー走れ!児童相談所2ー』をせせらぎ出版から再発行したもので、内容は同じです。(一部装丁、本文中のデータに変更あり)
大好評の『走れ!児童相談所』シリーズ第2弾
里崎が勤務2年目を迎える中央子ども家庭センターに、あの田丸が異動になってやってきた。キャラの異なる二人はチームを組んでケースに対応する。困窮した家庭を支援する一方、力及ばず壁にぶつかることも経験。そんな二人が次に直面したのは、卑劣な性的虐待だった。
本書は2018年3月にアイエス・エヌから発売された『光に向かって ー走れ!児童相談所2ー』をせせらぎ出版から再発行したもので、内容は同じです。(一部装丁、本文中のデータに変更あり)
2023年11月発売
2016年8月にメディアイランドから発売された『走れ!児童相談所』を
アイエス・エヌから装丁を変えて再発行し、せせらぎ出版が引き継ぎました。
今も愛される本書。内容は同じです
小説を読みながら児童相談所のことを学べる1冊!
三和県庁に勤める里崎は人事異動により、児童相談所勤務を命じられた。
そこで、初めて発達障害や児童虐待の実態に直面し、事の重大さに狼狽する。
次々と訪れる問題を抱えた家族や子どもたち。先輩たちとぶつかり合い、励まされ、
少しずつ成長する里崎の前に、深刻な虐待案件が待ち構えていた……
本書は、児童福祉司である著者が、体験もとに児童相談所の日常を描いた物語です。
困難にもかかわらず、明るくポジティブな職員の姿を通して、児童相談所の現状や課題を浮き彫りにします。
2016年8月にメディアイランドから発売された『走れ!児童相談所』を
アイエス・エヌから装丁を変えて再発行し、せせらぎ出版が引き継ぎました。
今も愛される本書。内容は同じです
小説を読みながら児童相談所のことを学べる1冊!
三和県庁に勤める里崎は人事異動により、児童相談所勤務を命じられた。
そこで、初めて発達障害や児童虐待の実態に直面し、事の重大さに狼狽する。
次々と訪れる問題を抱えた家族や子どもたち。先輩たちとぶつかり合い、励まされ、
少しずつ成長する里崎の前に、深刻な虐待案件が待ち構えていた……
本書は、児童福祉司である著者が、体験もとに児童相談所の日常を描いた物語です。
困難にもかかわらず、明るくポジティブな職員の姿を通して、児童相談所の現状や課題を浮き彫りにします。
2023年9月下旬発売
保育・福祉関係者はもちろん、教育関係者にもおススメしたい1冊!!
福祉からこぼれる子どもたちと、どうかかわればいいのか?
本書は様々な角度から、そのヒントを提示しています。重要なことは、子どもを支援対象者として見るのではなく、問題を発見し、解決に取り組む主体として認めることです。
※本書は2019年10月にアイエス・エヌから発売された『子ども・若者が創るアウトリーチ』をせせらぎ出版から再発行したもので、内容は同じです。(一部装丁、本文中のデータに変更あり)
保育・福祉関係者はもちろん、教育関係者にもおススメしたい1冊!!
福祉からこぼれる子どもたちと、どうかかわればいいのか?
本書は様々な角度から、そのヒントを提示しています。重要なことは、子どもを支援対象者として見るのではなく、問題を発見し、解決に取り組む主体として認めることです。
※本書は2019年10月にアイエス・エヌから発売された『子ども・若者が創るアウトリーチ』をせせらぎ出版から再発行したもので、内容は同じです。(一部装丁、本文中のデータに変更あり)
本書は、日本のオルタナティブ教育をめぐる現実、その学校づくりや法制化運動に参画しつつ、教育(学)のオルタナティブな志向を、超越性をめぐる問いにまで深めて探求してきた研究を編んだものである。これによって、ホリスティックな教育とケアに関する研究にも、寄与できるのではないかと目論んでいる。(「はしがき」より)
2022年4月1日発売
2022年4月、大阪公立大学の開学と同時に「サステイナビリティ(sustainability)」を学際的に追究する「現代システム科学域」の一学類として教育福祉学類がスタートした。本書は、前身となる大阪府立大学地域保健学域の枠組みで培ってきた学問成果を踏まえつつ、加えて新たな地域・国際社会が抱える持続可能性(サステイナビリティ)の人類的課題に対して、どのように教育福祉学が学問的に貢献できるかを考察するものとして企画されたものである。(「序文」より)
2022年4月、大阪公立大学の開学と同時に「サステイナビリティ(sustainability)」を学際的に追究する「現代システム科学域」の一学類として教育福祉学類がスタートした。本書は、前身となる大阪府立大学地域保健学域の枠組みで培ってきた学問成果を踏まえつつ、加えて新たな地域・国際社会が抱える持続可能性(サステイナビリティ)の人類的課題に対して、どのように教育福祉学が学問的に貢献できるかを考察するものとして企画されたものである。(「序文」より)
今こそ子どもたちの〝心の叫び〟と真正面から向き合い、そのパワーと可能性=「子ども力」をひきだすため、親、教師、学校、地域、社会が力を合わせ、前向きにかつ大胆に、やれることからやっていこうではありませんか。(「はじめに」より)
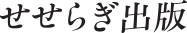
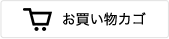
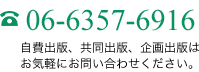

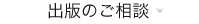


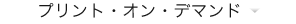

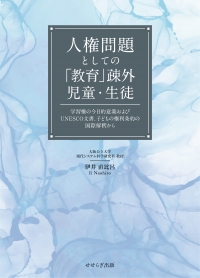


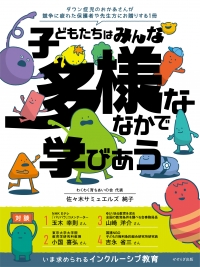
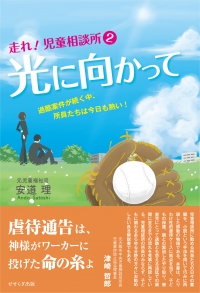
![[改装版]走れ! 児童相談所 ー発達障害、児童虐待、非行と向き合う、新人職員の成長物語ー](./product_img/1696560304-349924_s.jpg?r=1651660833)
![[改装版]子ども・若者が創るアウトリーチ ー支援を前提としない新しい子ども家庭福祉ー](./product_img/1693804409-027726_s.jpg?r=1987516094)